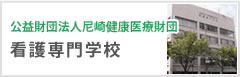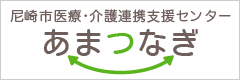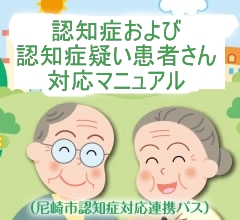「尼崎看護専門学校設立100周年を迎えて」(第661号令和 7年 1月 1日)
2025/01/25(土)
尼崎看護専門学校設立100周年を迎えて
公益財団法人 尼崎健康医療財団看護専門学校 学校長 橋本 創
尼崎看護専門学校は本年設立100周年を迎える。尼崎看護専門学校のルーツは大正14年(1925年)に設立された「尼崎産婆看護婦養成所」に遡る。大正14年3月12日に開催された尼崎市医師会臨時代議員会において承認された。設立者は尼崎市医師会の中馬興丸会長、所在地は尼崎市別所村260番地と記録されている。現在の建家町のあたりか。
太平洋戦争後、GHQの占領政策により医師会立の看護学校も機構を改めて再出発した。呼称も「尼崎市医師会附属准看護師養成所」と改められた。昭和27年から昭和49年まで医師会長が校長を務め、医師会員を中心にした講師、市内の民間病院での実習という今に至る形が作られた。この間の校長名を以下に記す(敬称略)。瀬尾正、西村保夫、大原重之、齋田正雄と歴代の会長名が並ぶ。当時の日本社会は戦後復興から高度経済成長期に入り看護師の需要が急速に拡大した時期であった。多くの学生は診療所のスタッフとして午前中は業務につき、午後から講義、実習を受けていた。このあたりのことは尼崎市医師会六十年史に詳しく記されている。
昭和49年(1974年)に尼崎医療センターの設立に伴って医師会立の看護婦養成所は廃止され医療センター附属の准看護学院(2年制、定員150名)ならびに高等看護学院(3年制、定員50名)が設立された。尼崎医療センターは水堂町3丁目に建設され新しい校舎で再出発することになった。初代の学校長は齋田正雄医師会長が就任、以後川崎文夫先生、小林繁郎先生、尾﨑馨先生と続いた。経営母体は尼崎市医師会から財団法人尼崎医療センターに移行したが、講義や実習は医師会員や民間病院に引き続き委ねられることになった。
平成13年(2001年)には看護科の課程変更を行い、看護科(3年制、40名)、准看護科(2年制、50名)の養成となった。医療の高度化に伴って急性期病院の看護師配置基準が7 : 1に引き上げられた影響で准看護師の実習病院の確保が困難となったことにより、平成22年(2010年)をもって准看護科は閉科となり85年にわたる准看護師養成は幕を閉じた。看護科は残ったものの1学年40名では経営が成り立たず、平成24年(2012年)看護科を70名に定員増を行い、3学年210名の構成となり現在に至っている。平成29年(2017年)には医療センターから聖トマス大学跡地の校舎に移転した。駅から少し距離はあるものの落ち着いた教育環境で学生たちは勉学に励んでいる。
私は平成31年(2019年)に尾﨑校長の後を受けて校長に就任しました。看護学校を取り巻く現在の状況について記してみたいと思います。
少子化の進行、大学進学率の上昇、若者の価値観や考え方が大きく変化したことにより受験生の数が激減している。専門学校は大学より就学年数が1年短く、看護師国家試験を早く受験できて早く就業できること、大学に対して相対的に学費が安いことがメリットとなってきた。このような時間的、経済的メリットにもかかわらず入学者の確保が困難となり定員割れする専門学校が増えてきている。残念ながら当校も過去2年は定員割れしている状況である。入学試験の倍率が下がってくると学生の質は必然的に低下してくる。看護師国家試験の合格率が受験生の学校選択基準の一つになることは理解できるため、教官のストレスも大きい。幸い、過去5年間の国試合格率は全国平均を上回っている。
また、令和4年にカリキュラムが改定され履修科目が追加された。3年間ですべてのカリキュラムを履修するには学生、教官の負担は大きい。看護協会は専門学校の4年制への移行を提言しているが全く否定するものではない。しかし、4年制への移行はスペースの確保、教官の確保などハードルが高く、医師会、看護協会、行政のバックアップなしでは実現は困難であろう。超高齢社会の中で、医療と介護の複合ニーズを持つ高齢患者が一層増加することが想定され看護師のニーズは今後ますます増加してくることは論を待たない。厚労省の推計では、兵庫県の2025年の看護師需給は4,380人不足するとされている。
尼崎看護学校の100年を回顧すると戦争や社会情勢の変化にもまれながらも、看護師を養成して地域医療に資するという医師会の強い意志を感じとることができました。尼崎看護専門学校の存在意義は地域医療を守るの一言に尽きると思います。
参考図書:「尼崎市医師会六十年史」
「百年」 一般社団法人尼崎市医師会